
|
となり、特徴ある天気現象が引き起こされるが、このような現象をブロッキング現象という。 気象庁予報部の天気予報指針によると、梅雨現象に関連させてブロッキング現象を説明している。それによると、日本付近は寒帯気団と熱帯気団の境目に当たるので梅雨現象が顕著に現れる。典型的な梅雨空の地上天気図は、図4.1のようにオホーツク海方面に高気圧、南の小笠原諸島方面にも高気圧があって、いずれも停滞している。日本付近はこれらの高気圧の谷間に当たり、前線が停滞し、小規模の低気圧が前線上を東進している。これに対応する上層の流れは図4.2のようになり、日本の西方には寒冷な空気の渦をその中に包括した深い気圧の谷が存在し、日本の東方は気圧の尾根となり、オホーツク海方面にブロッキング高気圧が形成されている場合が多い。この場合、強風帯(亜熱帯ジェット気流)は日本付近を東西に走り、一方、北の強風帯(寒帯前線ジェット気流)はブロッキング高気圧の北側の高緯度地帯をほぼ東西に走り、北太平洋上で合流している。「一般的には、中緯度、高緯度の偏西風帯の峯が発達してジェット気流が南北に分流し、分流点より下流の北側の停滞性の暖かい高気圧が形成されるような循環の状態をブロッキングと呼ぶ。そして北方の高気圧をブロッキング高気圧という。しばしば共存する高気圧の南側、あるいは谷場に形成される低気圧を切離低気圧、または寒冷低気圧と呼んでいる。ブロッキングの状態は基本的には分流型と南北流型に大別される。」発現時についての調査によると、強いブロッキングは冬季に頻発し、小規模のブロッキングは、春、梅雨期、秋に頻発する、 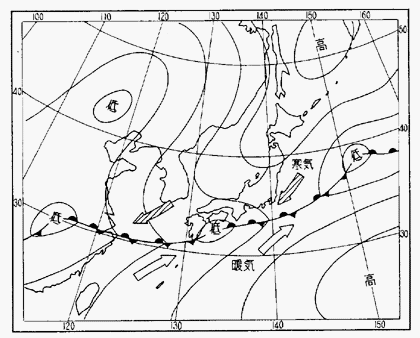
図4.1 梅雨の典型的な地上天気図 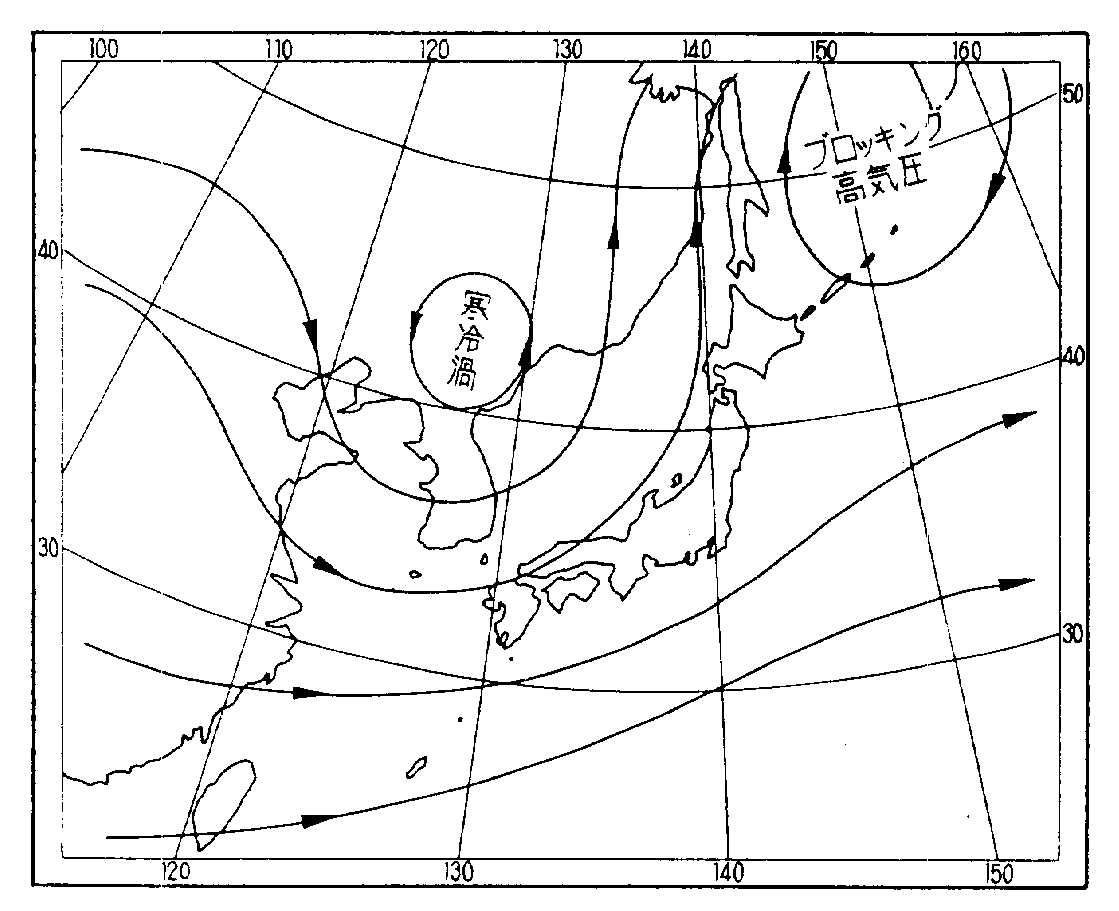
図4.2 梅雨の典型的な高層天気図 前ページ 目次へ 次ページ
|

|